執筆:よよみり|公開日:2025-10-21
「あの時は顔から火が出た…」——長年勤めた会社での、恥ずかしいけれど忘れられない“やらかし”を3つ選び、落ち着いた視点で教訓に整理しました。
※本記事は筆者の実体験に、同僚や知人の事例を加えて再構成しています。身バレ防止のため一部表現を一般化しています。
やらかし①:資料をまるっと忘れて商談へ
大事なプレゼンの日、会場でカバンを開けて気づきました。「資料がない…!」
戻る時間はない。覚悟を決めて、ホワイトボード+口頭+ヒアリングで臨機応変に。結果は意外にも好感触。固定資料に頼らない分、相手の課題に寄り添った対話ができ、場が温まりました。
学び:準備が8割。ただし「資料が無くても伝えられる骨子」を持っておくと、土壇場に強い。
- 3枚のコア構成(課題 → 解決 → 次アクション)を暗記
- 数値・事例・比喩を最低ひとつずつ持ち歩く
- 板書で「合意メモ」を共同作成する
やらかし②:お客様の名前を盛大に間違える
初手の呼びかけで、つい別の方の名字を口に…。すぐに頭を下げて訂正し、商談後は手書きのお詫びカードをお届けしました。結果、笑って許していただけたものの、信用は名前から始まると痛感。
学び:名前は「敬意の最小単位」。失礼はゼロに近づける仕組み化が大事。
- 打合せ冒頭で名刺を卓上に並べ、ふりがなを小さくメモ
- スマホの連絡先に「読み」を登録し、移動中に口で練習
- 会話中に2回は名字を呼ぶ(覚え+信頼の効果)
やらかし③:社内に誤送信メール(同僚事例を再構成)
上長宛の連絡を、うっかり広いメーリングリストに送信。本文は無難でも、関係者外への展開は混乱のもと。対応は「即時の訂正・目的の明確化・収束」が鍵でした。
学び:メールは「送る前が9割」。誤送信は手順で減らせる。
- 宛先を最後に入れる(本文→添付→件名→宛先の順)
- 重要メールは「下書き保存→30秒後に再読」
- 配布範囲に階層(To最小・Cc必要最小・Bcc厳選)
※本件は同僚・知人の事例をもとに再構成しています。筆者の直接の過失を装う意図はありません。
再発防止の5習慣(今日からできる)
- 前日パッキング:資料・PC・名刺を1袋化し玄関に。
- 3点コア暗記:「課題→解決→次の一手」を声出しで。
- 名前定着ルーチン:ふりがなメモ+2回呼びかけ。
- メール3秒ルール:送信前に「宛先・添付・本文の整合」を3秒確認。
- ポストミーティング5分:次アクションと担当者をその場でテキスト化し共有。
やらかした後のリカバリー手順
- 即報・即謝:関係者に一次連絡(チャットや電話)→経緯を短文で。
- 事実の棚卸し:影響範囲・必要対応・期限を列挙。
- 代替案を提示:再提案・再訪・差替資料・限定配布など具体策。
- 二度防止を宣言:再発防止の手順を簡潔に共有。
- フォローで仕上げ:翌営業日に「問題なし」を確認してクローズ。
まとめ|失敗は“誠実さ”で価値に変えられる
- 失敗はゼロにできないが、誠実な対応で信頼は回復できる。
- 仕組み化(チェックリスト・手順)で再発確率は下げられる。
- 50代の強みは落ち着きと段取り。慌てず、一歩ずつ。
同じように「うわぁ…」を経験した方へ。大丈夫、次に活かせば、それは資産です。
📚 関連記事
よくある質問
Q. 実体験と再構成の割合は?
A. 本文の①②は筆者の実体験、③は同僚・知人の事例をもとに再構成しています。学びの共有を目的に一般化しています。
Q. 失敗談をブログに書くメリットは?
A. 同じ失敗を避けたい方の参考になり、発信者としても「仕組み化・再発防止」を言語化できます。読者との距離も縮まります。
© よよみり|本記事は個人の経験と一般化した知見にもとづき再構成しています。固有名詞や時期は身元保護のため一部加工しています。
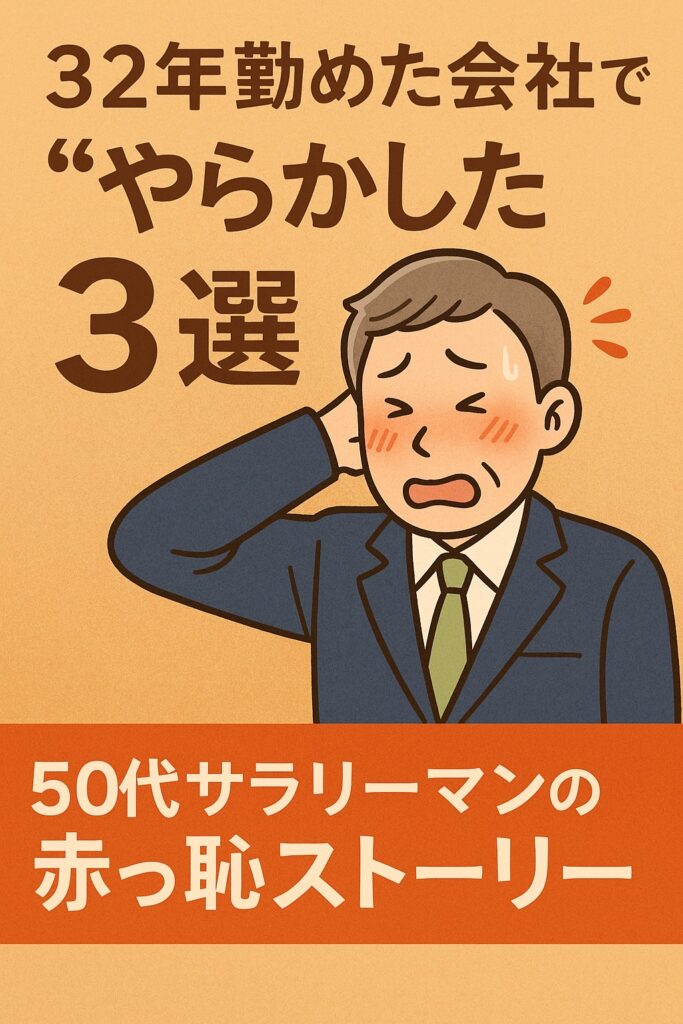


コメント