公開日:2025-11-3|執筆:よよみり
50代からの新NISAは「どの証券口座を使うか」で使い勝手も成果も変わる。結論を先に。
SBI証券と楽天証券の併用が最適です。
- 楽天証券:投信・UIが強い。楽天ポイント活用。
- SBI証券:米国株・ETF・外貨周りが強い。
以下、実際に両方使っている立場で差を短く、はっきり示します。
※UI(ユーザーインターフェース)とは、ユーザーが製品やサービスを使うときに触れる「操作画面やボタン、メニュー」などの接点のことです。たとえばスマホやパソコンの画面上の見た目や操作部分全般を指します。簡単に言うと、「人と機械やソフトをつなぐ窓口」のような役割です。
結論|両方開設して使い分けるのが最速
要点
- 投信・ポイント投資=楽天証券
- 米国ETF・外貨コスト=SBI証券
- 迷う時間より、両方作って運用を回すほうが早い。
☑ 50代の新NISAは楽天証券が向いています
新NISAを始めるなら、楽天証券の口座開設からスタートするのが最短ルートです。 クレカ積立+楽天ポイントでの投信購入が50代と相性抜群。
SBI証券 vs 楽天証券(要点比較)
| 比較項目 | SBI証券 | 楽天証券 |
|---|---|---|
| 投信の積立設定 | 自由度高い | アプリ完結で簡単 |
| ポイント投資 | V/d対応 | 楽天ポイント強い |
| 外国株・ETF | 最強クラス | やや少なめ |
| 外貨コスト | 住信SBI連携で安い | 標準的 |
| アプリの使いやすさ | 高機能だが複雑 | 直感的で見やすい |
※住信SBIネット銀行の現在の銀行名は「住信SBIネット銀行株式会社」で、2025年10月1日からはNTTドコモの連結子会社となり、サービスブランド名が「d NEOBANK」に変更されています。ただし正式な銀行名自体は変わらず「住信SBIネット銀行株式会社」のままです
SBI証券|強み・弱み・実感
強み
- 米国株・ETFの銘柄数が多い。情報も集めやすい。
- 住信SBIネット銀行と組むと外貨コストが低い。
- ポイントはV/dに対応。IPOやiDeCoも強い。
弱み
- アプリが高機能=初心者には複雑に映る。
- 投信画面は情報量が多め。慣れに時間が要る。
使っての本音:慣れたら強い。米国ETFや外貨周りはSBI一択でいい。
楽天証券|強み・弱み・実感
強み
- アプリが素直で見やすい。投信の積立管理がラク。
- 楽天ポイント投資と相性が良い。心理的ハードルが低い。
- カード積立でポイント還元(条件は時期で変動)。
弱み
- 外国株・ETFの品揃えはSBIに劣る。
- ポイント還元の細かい条件は変動に注意。
使っての本音:投信メインなら楽天が速い。画面が素直で迷わない。
目的別の使い分け
- 投信・積立初心者:楽天証券
- 米国ETF・分散強化:SBI証券
- 国内高配当株:SBI証券
- ポイント活用:楽天証券
- 家族運用・最適化:両方開設
どちらも魅力的ですが、50代から新NISAで実際に成果を出すなら 楽天証券の口座開設が 最も行動の近道になります。
🔗 私が実際に使っている証券口座
- 楽天証券|投信・ポイント投資に最適
- (SBI証券は提携後に追加予定)
※本リンクは広告を含みます。筆者も実際に利用中です。
楽天証券:新NISA・イデコ口座、オルカン+S&P500中心の積立。
SBI証券:積立NISA時代に購入した特定口座:国内高配当株と米国ETF。外貨コストを抑えて拾う。
結論:両方の“良いとこ取り”で迷わず回すのが一番速い。
💳 楽天証券を使うなら楽天カードがおすすめ
楽天証券で投資信託を積立てるなら、楽天カード決済が便利です。
楽天カード決済のメリット:
- 💰 積立額の0.5〜1.0%がポイント還元
- 🎁 毎月最大5万円まで決済可能
- 📊 年間最大6,000ポイント獲得
- ⚡ 引き落とし日が後なので資金効率が良い
- 🆓 年会費永年無料
私も楽天証券×楽天カードで積立中。毎月500〜1,000ポイントが自動で貯まっています。
※本リンクは広告を含みます。年会費永年無料です。
口座開設の流れ(どちらもオンライン完結)
- メール登録 → 本人確認書類アップロード
- マイナンバー入力 → 申込送信
- 審査完了後にログイン情報が届く
悩む前に両方作っておく。これが一番早い。
まとめ
- 投信は楽天、米国ETFはSBI。役割分担が最短。
- 50代は“操作の軽さ”と“コスト最適化”を両立すべき。
- 結論:両方開設して使い分け。以上。
比較した結果、あなたが新NISAで着実に資産を作りたいなら、 まずは無料で口座を開設することが大事です。 楽天証券はネットで完結+非課税メリットをフルに活かせます。
関連記事
- • 楽天証券で新NISAを始める手順
- • 【楽天カード×新NISA】50代でもムリなく続けられるクレカ積立の始め方
- • オルカン vs S&P500|50代向け投信比較
- • 50代の家計見直しと投資の黄金バランス
※本記事は情報提供であり、特定の投資行動を勧誘するものではありません。最終判断は自己責任でお願いします。
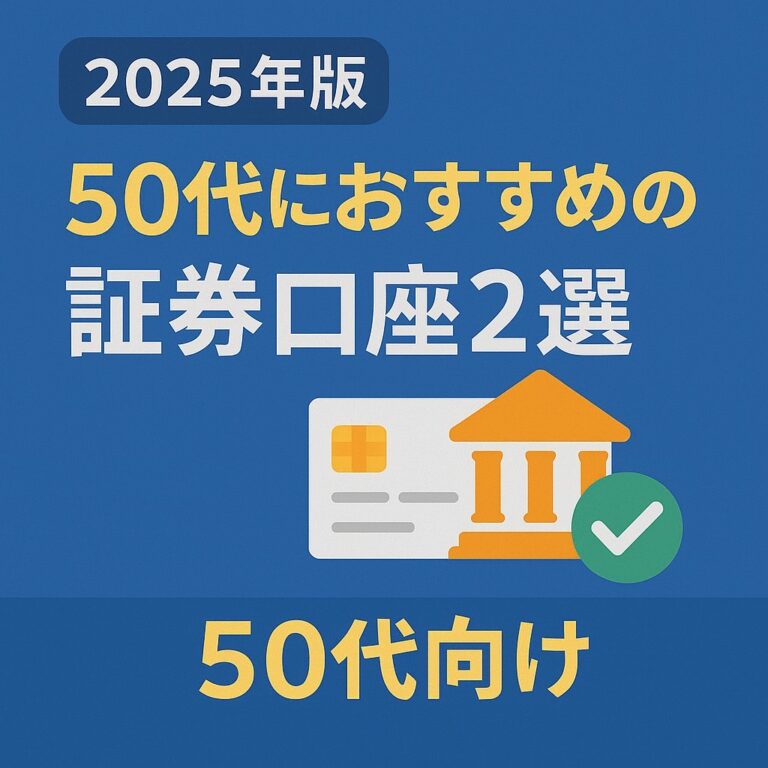

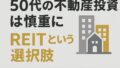
コメント